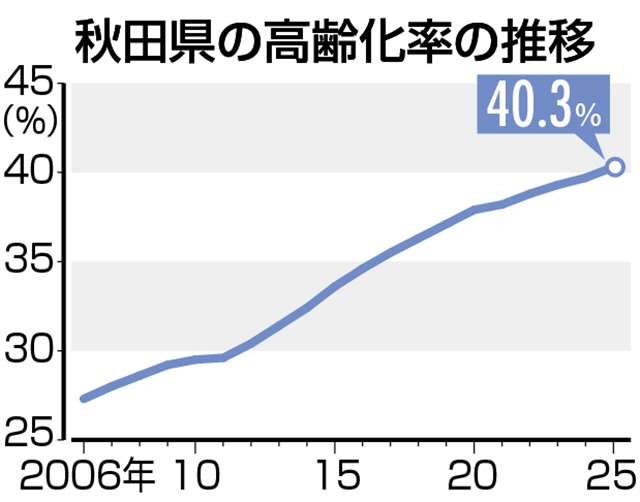2日に能代山本地方を襲った記録的大雨で、能代市を流れる悪土川が氾濫しました。
流域の松長布 などで多くの住宅の浸水被害が発生しており、詳しい状況は調査中ですが、自宅周辺が冠水して動けなくなった一部の住民が、消防のボートで救助されるなどしました。
悪土川流域では5年7月の大雨で住宅100戸以上が床上浸水し、これまで何度も水害が発生。
国と県、市が防災・減災を目指した「悪土川水害対策プロジェクト」を進めている最中に被害が繰り返される事態となりました。
悪土川は同市坊ヶ崎地先を上流部に、 同市下悪戸地内の早川水門で米代川に接続する延長約2キロの河川。
本流は松長布、大内田、下古川布、下内崎と水田を貫くように流れ、流域には水田等を埋め立てて開発された住宅地が張り付きます。
<三浦個人の意見/感想です>
いくら対策を講じても自然災害、特に河川の氾濫だけはどうにも打つ手はありません。
記録的な大雨となれば尚更のことでしょう。
川という自然の恵みは時に災いをもたらしてしまいます。
対策プロジェクトは良いのですが、実際に災害にあってしまった時にこそ国の直接支援を期待したいのです。
そう感じているのは僕だけではないと思います。
皆さんも何かお知恵をお貸しください。
皆様も投稿記事への感想やご意見など何でもご自由にコメントし、
コミュニケーションしませんか。
※ この画面を下ヘスクロールするとコメント欄が表れます。
この投稿記事に対して誰でもが何人でも自由にご自分の考えや思ったことを
コメントできます。
また、そのコメントに対して誰でもが何人でも自由に返信コメントができます。
投稿記事をテーマにしてコミュニケーションしましょう。